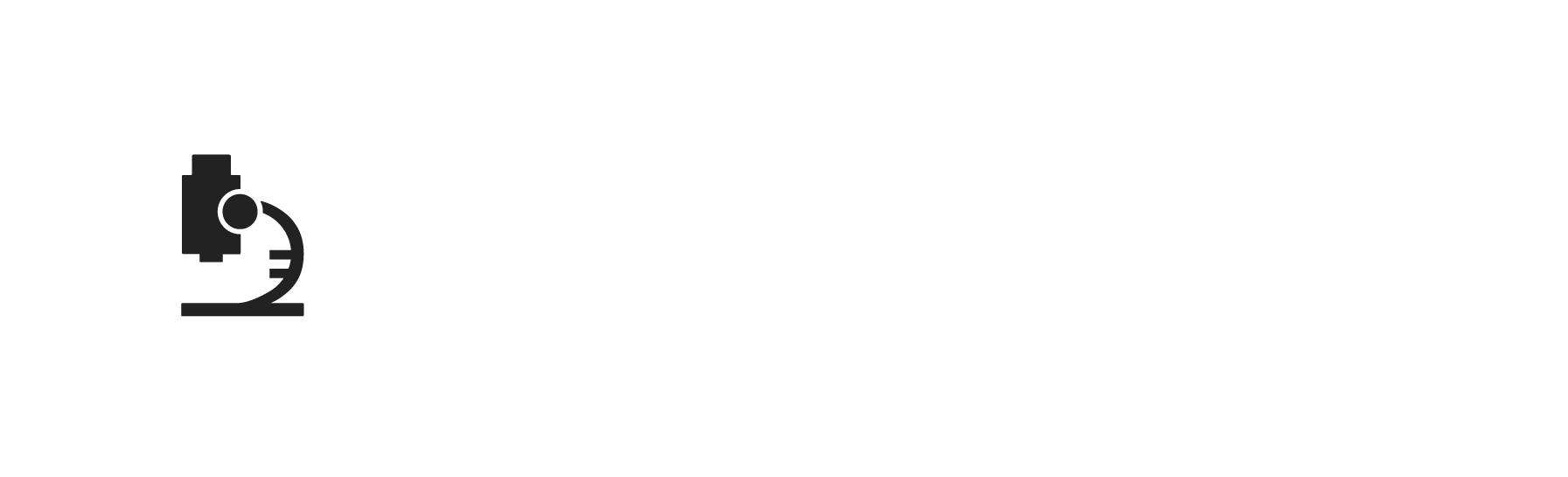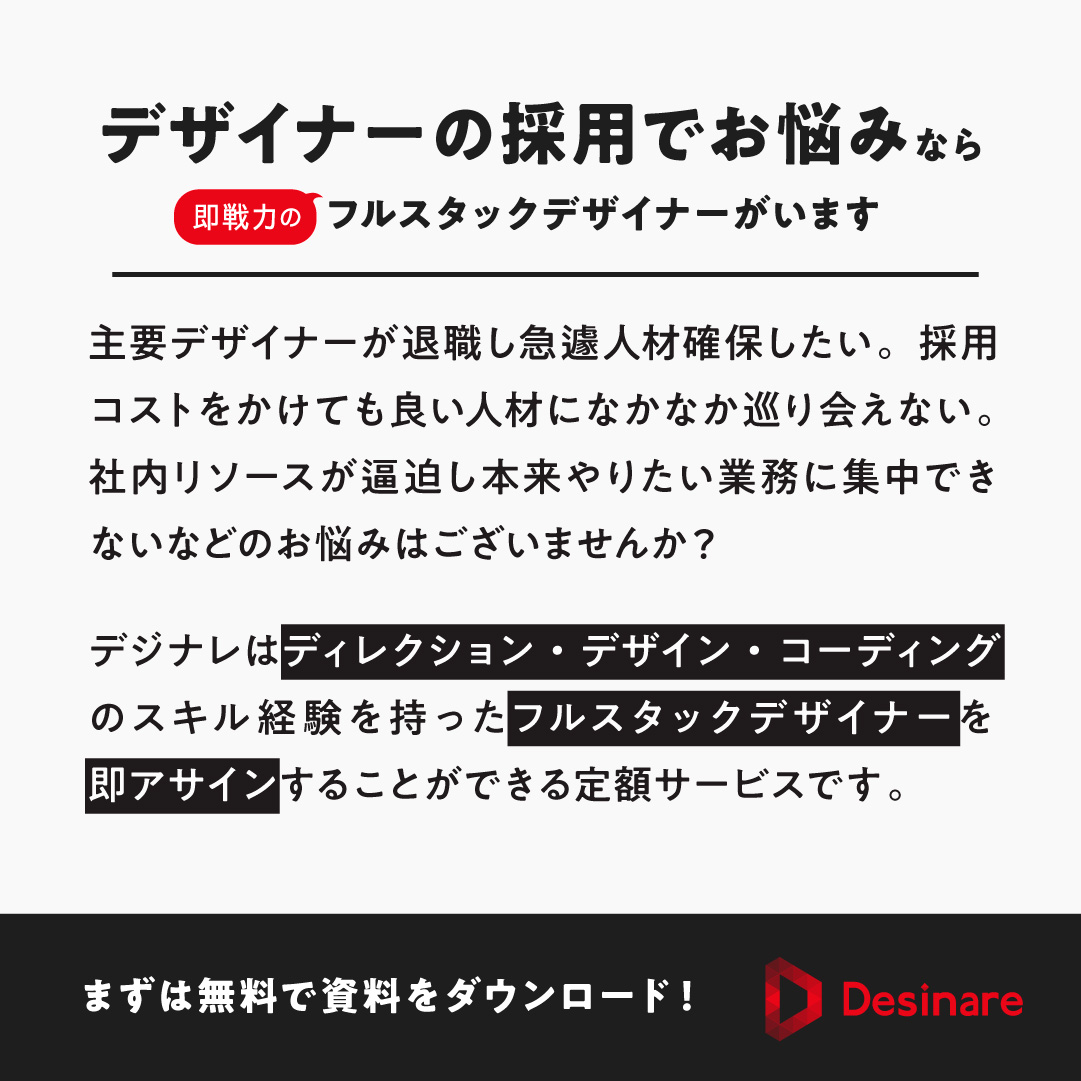アップルやダイソンなど大手企業でも取り入れられているデザイン経営。
興味はあるけど具体的に何をやれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事ではデザイン経営に関してその特徴をまとめ、自社にデザイン経営を取り入れる際のヒントをご紹介します。
- デザイン経営に興味がある方
- デザイン経営を取り入れたい方
- 会社のブランド力を向上させたい方
- 会社でイノベーションを起こしたい方
これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めば、デザイン経営の特徴がわかり、どう会社に取り入れていけば良いのかがわかりますよ。
デザイン経営とは

デザイン経営とはデザイン思考を事業プロセスの中に組み込む考え方のことです。
単純に良いデザイン、センスのあるデザインを作るのではなく、ユーザーの立場に立って、市場のニーズを正確に捉え開発を行なっていく必要があります。
デザイン経営が実現することにより組織の経営課題を解決することができ、ブランド力やイノベーション力の向上が期待できます。
合わせて読みたい>>デザイン経営とは【定義や実践方法を分かり易く解説】
デザイン経営が注目されている理由

近年どの産業もITの技術革新が進んでいて、上質な海外製品も増えたことから競争も激化。従来の手法では顧客のニーズを素早くキャッチしカタチにしていくことは困難になっています。
このような状況の中で生き残っていくためには、顧客に企業の目標や価値観を発信し、受けれてもらう必要があります。
デザイン経営ではそのような企業の価値観をデザインで表現することができるため、企業価値を多くの顧客に知ってもらうことができるのです、
デザイン経営の特徴

そんなデザイン経営についてその特徴に触れながらもう少し深掘りしていきましょう。
デザイナーが最上流から参画する
経済産業省・特許庁が発表した「デザイン経営宣言」にもあるように、デザイナーは経営チームに参加し、事業戦略構築の最上流から関与していく必要があります。
デザイン責任者が製品やサービスをユーザー視点でとらえ、その中で業務プロセスに変更が必要な場合は改善を促します。
そしてそれを経営層にも共有することで、会社全体でデザインの視点が構築され、目指すべき方向性を明確化することができます。
ウォーターフォール型からアジャイル型へ
アジャイル開発とはプロジェクトを小さなサイクル分け開発工程を繰り返す開発手法のことです。優先度の高い要件から開発を進め、開発した各機能を集合させて1つのシステムを構築していきます。
かつては「企画・要件定義・設計・実装・テスト」と滝のように上から下へと開発を進めるウォーターフォール型の開発が主流でした。
しかしウォーターフォール型の開発では原則として前の工程に戻ることができないため、万が一欠陥が見つかった場合に、柔軟に対応することが難しいというデメリットがあります。
一方、アジャイル型では「プロジェクトに変化はつきもの」という前提のもと、期間内であれば途中で仕様変更を行うことができます。これにより開発までのスピードを大幅にアップしていくことができ、ビジネスを素早くスタートすることができるのです。
デザイナーが顧客の潜在ニーズの発見を主導する
デザイナーは顧客が持っているニーズを引き出し、それを解決する存在です。例えば中国最大のECプラットフォームであるTmallは、毎年11月に開催されるセールにて、スケッチャーズ、リーボックなどといったブランドの靴を1足ずつ購入できるようにしました。
これにより、片足を切断した身体的な障がいを持つ方でも、買い物がしやすくなったのです。
デザイナーは単に見た目の良いものを作るわけではありません。社会やユーザーの問題に目を向け、どうしたらその問題を解決できるのかを主導して考えていく必要があるのです。
コトバにならないものをカタチにする
デザイナーは会社の思いやユーザーのニーズをカタチにして具現化する力があります。もしデザイナーがいないまま会議が進められてしまったら、アイディアがなかなかカタチにできず、開発が先に進まない可能性があります。
しかし、デザイナーが上流工程から参画するデザイン経営では、アイディアが可視化され、それによって他のアイディアを促すファシリテーション効果も期待できます。
まとめ
いかがでしたか。本日はデザイン経営に関してその特徴をまとめていきました。
デザイン経営は経営にデザイン思考を取り入れることであり、ユーザーの立場に立って、市場のニーズを正確に捉え開発を行なっていく考え方でした。
デザイン経営を行う際は、上流工程からデザイナーが参画をすることで、会社全体でデザインの視点を持つことができるのはもちろん、顧客目線で本当に必要なものを開発していくことができます。
デザイン経営を行うことで、ブランド力の向上やイノベーションを生み出すことができます。これからの時代にはなくてはならないデザイン経営。ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。