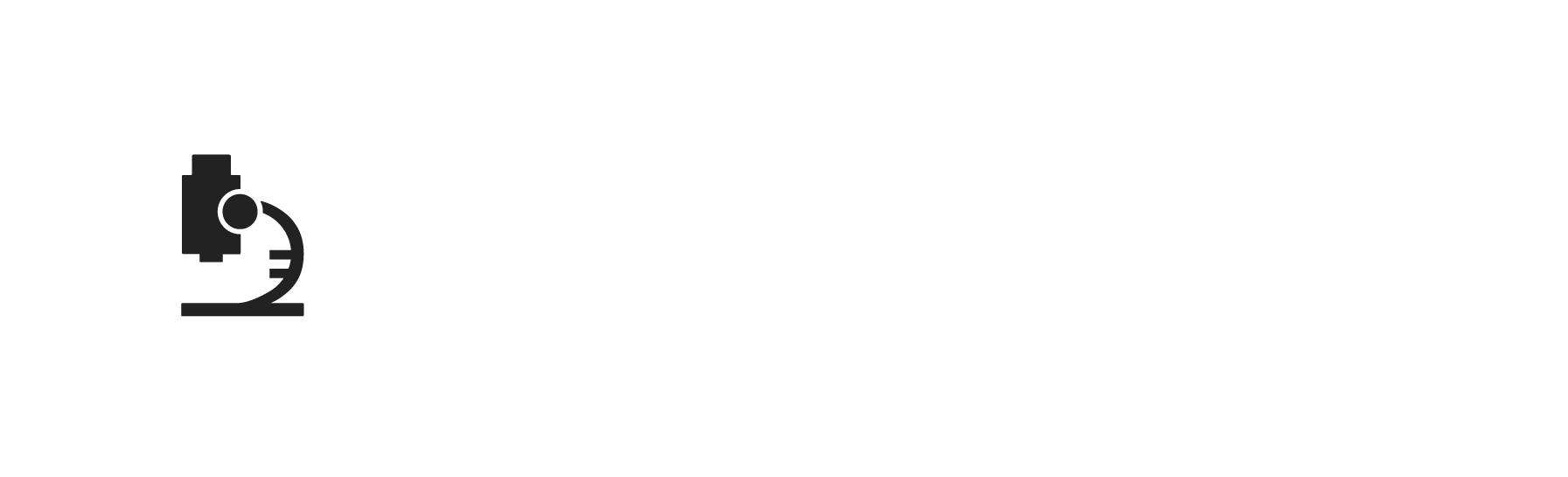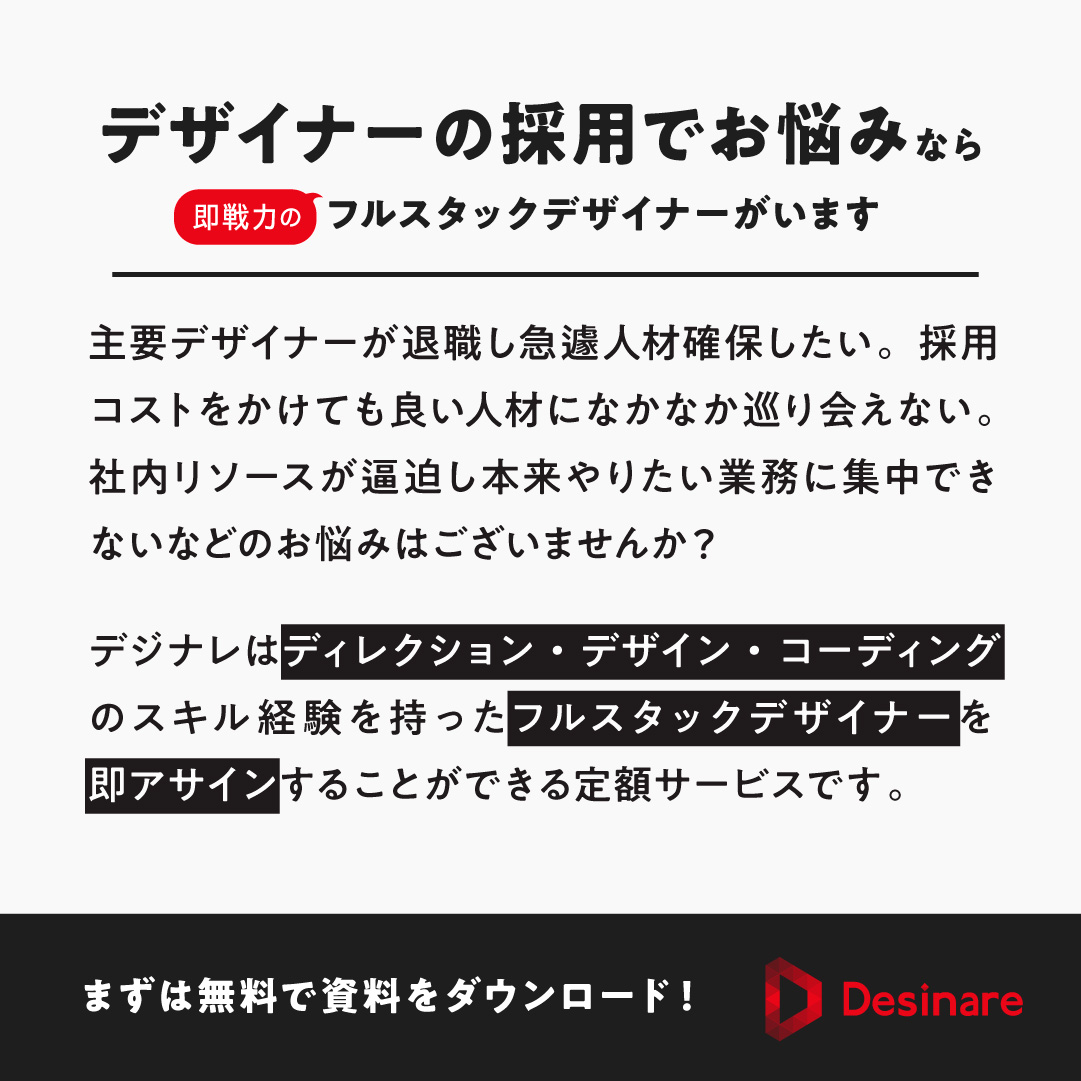時代の変化とともにデザインの在り方は大きく変化しています。
この記事ではそんな「デザイン」の変化に関して、年代別に振り返っていきたいと思います。
- デザインの変遷について知りたい方
- デザイン経営に興味をお持ちの方
- 自分のビジネスにデザインを取り入れたいと思っている方
これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばデザインが時代の流れとともにどのように変化していったのか、その歴史を知ることができますよ。
〜1950年:アーツ・アンド・クラフツ運動

18世紀半ばから19世紀に渡るイギリスの産業革命では大量生産によって安価で粗悪な商品が世の中に多く出回るようになりました。
その動きに対して工業と伝統の統合を掲げるアーツ・アンド・クラフツ運動がイギリスのウィリアム・モリスによって行われるようになりました。
ウィリアム・モリスは「労働の喜びが生きていた中世の社会にならって、伝統的な職人芸を見直し、芸術的な手仕事による美しい日常品や生活空間をデザインし、供給することで、人々の生活の質を向上させる」と述べています。
こうしたアーツ・アンド・クラフツ運動は1919年に生まれるバウハウスへと継承されます。
第一次世界大戦後のドイツでは機械産業を中心に近代社会に適した芸術と産業を掛け合わせた活動が推進されていました。そんな時代の中、ドイツ工作連盟で活動していたグロピウスがワイマール共和国にバウハウスを設立させたのです。
バウハウスではグロピウスを中心に独自の教育システムが行われました。具体的には基本教育コースと実技コースの2つのコースで、実技コースに進むと、工房で木工や金工、ガラスなどといった実践的な内容が学べるというものでした。
こうしたアーツ・アンド・クラフツ運動、バウハウスは今日の私たちのモダンデザインの礎だと言われていて、現代のデザインにも大きな影響を及ぼしています。
1950年〜1960年代:デザインサイエンス

バックミンスター・フラーは1950年代半ばにデザインサイエンスを提唱しました。
デザインサイエンスとは細分化、専門化する既存の学術体系に対して人間本来の分断されない包括的な知覚で、持続可能な人類の発展のために必要な発明を行うことを指します。
また北欧では参加型の共創デザインアプローチが登場します。デザイナーはファシリテーターの役割を果たします。
1960年〜1980年代:コンピューターの登場

この時代になるとコンピュータが登場します。その中で、HCI(ヒューマン-コンピュータ・インタラクション)という考え方が生まれ、デザインの対象がモノを扱う際の行為や相互作用へと変化していきました。
HCI(ヒューマン-コンピュータ・インタラクション)とは人とコンピュータの関わり合いのことで、人間の心理的身体的持続性と、コンピュータ技術、社会環境などを複合的に扱っていく考え方のこと。
またコンピュータで情報を扱うことが日常化していくにつれ、よりユーザー目線で情報を設計することが重要視されるようになりました。
この考えを人間中心設計(Human Centered Design)と言います。
人間中心設計(Human Centered Design)では以下の6つの原則があります。
- ユーザー、タスク及び環境の明確な理解に基づいて設計
- 設計と開発全体を通してユーザーが参加
- ユーザー中心の評価に基づいて設計を実施し、改良
- プロセスの繰り返し
- ユーザー体験全体を考慮して設計
- 専門分野の技能及び視点を含む設計チーム
調査→分析→設計→評価という4つのサイクルを繰り返し、徐々に完成度を高めていくことが重要です。
1980年〜2000年代:無形サービスへのアプローチ

無形のサービスに対してのインタラクションが注目され始めます。1980年代に、マーケティング研究者のリン・ショスタックがサービス設計の方法に関して論文を発表しています。
この中で、製品やサービスが顧客に提供されるプロセスを可視化するツールとしてサービスブループリントというフレームワークについて紹介しています。
また、ロバート・F・ラッシュとスティーブン・L・バーゴは2004年にサービスドミナントロジックを提唱しています。
サービスドミナントロジックとはサービスが支配的な論理であり、すべての経済活動はサービス活動であるという考え方のことです。
このサービスドミナントロジックでは、企業が顧客に対して提供する商品を、有形・無形に分けるのではなく顧客のニーズを捉えて満足させるものとしてひとくくりに考えます。
こうしたサービスデザインの普及によって、非デザイナーをデザインプロセスに参加させる動きが加速します。
2010年〜:UX概念の広まり

またこの時代になると、インターネットが一般家庭にも普及し、AmazonやGoogleなどといったサービスが登場します。こうした動きはインターネットを利用した情報発信や購買活動を促進することになります。
こうした動きからPCやWebサイトにおけるユーザービリティが注目されるようになり、UXの概念が広まっていくのです。ビジネスにおいてもいかにUXをデザインするかが競争力を高める課題となっています。
例えばアップルは製造を委託先に任せるのではなく、社内にデザイナーを配置し優れたUXで注目を浴びるようになりました。
製品は「キーノート」と呼ばれる発表会でお披露目し、ジョブズはこれに2ヶ月を費やします。発表会までも徹底的にデザインしてくこだわりよう。
そして、新商品は美しいデザインが施された直営のアップルストアで販売されます。このように商品はもちろん、顧客の購入体験までもデザインするのです。
こうした動きはデザインが企業や組織全体としての取り組み、活用していくべき資産としての位置付けに変わったことを示しています。
こうした組織全体の位置付けとしてのデザインでは、デザイナーは他部門を巻き込んで、事業運営の方針を生み出していくリーダーシップが必要不可欠なのです。
デザイン思考の発展

今まで時代ごとのデザインのあり方を振り返っていきました。時代の流れとともにデザインがビジネスにおいて重要視されるようになってきたわけですが、こうした背景にはデザイン思考の発展が影響しています。
デザイン思考とはユーザー目線に立って、市場のニーズを把握することで必要なサービスを考察していく考え方のことです。
様々な場面や状況はもちろん、サービスや多くの製品に応用が可能なことから数多くの企業で取り入れられるようになりました。
IBM社では2012年にデザイナーを5年間で1000人雇用する計画を発表しています。デザイナーの採用強化はもちろん、組織内でもデザイン部門を立ち上げ新人デザイナーや非デザイナー向けに短期間研修プログラムなどを行なっています。
Capital One社は2014年に米国デザインファームAdaptive Path社を買収しています。Adaptive Path社はデザインプロジェクトのみならず、加えて、UX Week、UX Intensiveといったトレーニングプログラムを行なっています。
また2018年5月には経済産業省・特許庁が「デザイン経営宣言」を発表。これにより「デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営」が加速するようになりました。
2020年には内閣府の「成長戦略実行計画」の中に社会人の創造性育成の重要性として「デザイン」という言葉が利用されるようになり、政府としてもデザイン思考を推進していくことがわかりました。
こうした背景もあり、現在多くの大学でデザイン思考、デザイン経営の教育が行われています。
東京理科大学では国際デザイン経営学科を設け、経営学のみならず、デザイン技術やテック技術の習得などを行なっています。
武蔵野美術大学や多摩美術大学などでもビジネスを学ぶ学部、スクールなどが誕生しています。
新しいデザインアプローチ

デザイン思考がユーザー観察が問題解決のアプローチであるが故に、全く新規のイノベーションには向いていません。そのような状況の中で、新しいデザインアプローチが提唱されています。
イタリアミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授は「デザイン・ドリブン・イノバーション」を提唱しています。
「デザイン・ドリブン・イノバーション」はユーザー観察はしつつも、モノの意味を追求してイノベーションを実現する方法のことです。
ユーザーが使いたいものを提供するのではなく、技術イノベーションを伴いながら、その商品に意味のイノベーションを見出します。
「ユーザーにとってなぜ必要なのか?」「自分にとってそれはどのような意味合いなのか?」など問いかけ、新たな解釈や価値を提供するのです。
また、フランスでは既成概念にとらわれずに自由な発想を大切にするアート思考が注目されています。
多様性が求められる現代において、新しい概念をクリエイティブすることで独自性のあるサービスを展開することができます。
まとめ
いかがでしたか。本日はデザインの変遷に関して、時代の流れとともに振り返っていきました。
デザインは、モノから抽象的な体験やサービスが対象に変化していきました。その中でデザイナーではない人たちがデザインに参画するデザイン思考が普及していったのでしたね。
これによってデザインは組織的に活用する戦略的リソースになっていったのです。
時代の流れとともにデザインの在り方は変化を続けています。ぜひ社会の変化をいち早くキャッチし、ビジネスに最適なデザインを模索していただければと思います。